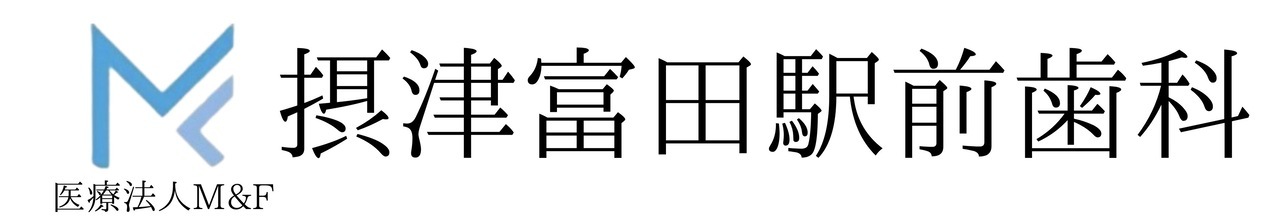| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
休診日:日曜・祝日
お口の中がパサパサ!その正体は?

突然ですが、皆さんのお口の中は乾いていませんか?お口の中が乾いていると感じている人は、もしかしたら口腔乾燥症かもしれません。口腔乾燥症はお口の中が乾いているというのが主な症状です。しかし、その中に実は恐ろしい全身的な病気が隠れていることもあります。このため、口腔乾燥が気になる方や自分の周りにお口の乾燥を訴える方がいらっしゃれば、ぜひ一度お口の専門家である歯医者さんに相談してみてもいいかもしれません。
目次
①口腔乾燥症とは?
-唾液をつくる唾液腺とは?
-実は健康な人でもお口が乾く時がある!
②口腔乾燥による弊害
-多くの歯が虫歯になりやすくなる
-粘膜が傷つきやすくなる
-物が飲み込みにくくなる
③口腔乾燥の原因
-加齢
-糖尿病
-ストレス
-口呼吸
-お薬の影響
-シェーグレン症候群
④口腔乾燥への対応
⑤まとめ
①口腔乾燥症とは
皆さんのお口の中は常に唾液によって湿潤な状態が維持されています。唾液は唾液腺と呼ばれる唾液を作る専用の組織によって作られます。お口の中が乾燥するとは、なんらかの原因によって、一過性または、永続的に分泌量が低下しています。
■唾液を作る唾液腺とは?
唾液はお口の中の潤いを保つだけでなく、細菌の増殖を抑えたり、食べ物を飲み込みやすくしたりとその機能は様々です。そんな唾液はどこで作られるのでしょうか。それは「唾液腺」です。唾液腺は「大唾液腺」と「小唾液腺」の2種類に分けられます。これは単に目で見た時の大きさによって分けられます。大唾液腺は3つあります。耳の前にある耳下腺、顎の下にある顎下腺、舌の下にある舌下腺です。小唾液腺はお口の中の粘膜のあちこちに存在します。
これらが、しっかりと機能することで、唾液は絶えず作られて、お口の中が潤った状態で維持されます。
■実は健康な人でもお口が乾く時がある
口腔乾燥は文字通り、お口の中が乾く病気です。しかし、健康な方であってもお口の中が乾くことがあります。一体どんな時でしょうか?
それは「緊張している時」や「脱水症状になっている時」です。この2つは本質的には状態が異なります。緊張している時にお口の中が乾いているのは、唾液の分泌量が少なくなっているからではありません。唾液の性質が普段と変わるからです。唾液の性質は2種類あり、サラサラした唾液とネバネバした唾液があります。緊張している状態では、ネバネバした唾液が多くなり、お口の中が乾燥しているように感じます。また、脱水症状の時などは唾液を作るための水分が不足しているため、一過性に分泌量が少なくなります。
このように口腔乾燥は唾液の量はもちろんですが、唾液の性質によっても感じます。ですので、一口に口腔乾燥と言っても正しい検査と診断が重要になります。
②口腔乾燥による弊害
さて口腔乾燥はどのような悪影響を与えるのでしょうか?ただ口の中が乾くだけではありません。それは唾液がお口の中で様々な機能を担っているからです。いくつか詳しく見てみましょう。
●多くの歯が虫歯になりやすくなる
唾液には、殺菌作用を持つ成分が多く含まれています。このため、私たちは、簡単に虫歯になりにくいお口の中が維持されています。しかし、口腔乾燥で唾液の分泌が少ないとどうでしょうか?簡単にイメージできると思いますが、虫歯の原因菌を増やさないような成分が不足し、虫歯になりやすくなります。これは、虫歯だけでなく、歯周病についても同様です。実際、唾液の分泌が少ない方は、多数歯に及ぶ虫歯を患っている方も少なくありません。
●粘膜が傷つきやすくなる
唾液には、お口の中の粘膜を保護する成分が含まれています。唾液が少ないと食べ物や歯磨き、入れ歯などの外部からの刺激によって口腔粘膜が傷つきやすくなります。また、それだけでなく、刺激に対する抵抗も少ないため、傷の治りも遅くなる傾向になります。
●物が飲み込みにくくなる
おからなどを食べた際に飲み込みにくい経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか?唾液は、食事の際に欠かせません。なぜなら唾液によって食べ物をコーティングし、飲み込みやすい形にしているからです。このため、口腔乾燥を訴える方は、ご飯が飲み込みにくいと感じることも少なくありません。
今回紹介したもの以外にも、様々な弊害があります。普段意識することは少ないと思いますが、唾液は非常に多くの役割を持っており、それが少ない状態ではいかに生活がしにくいかイメージできたでしょうか。
③口腔乾燥の原因
ここで口腔乾燥はなぜ生じるのでしょうか?次に原因について解説しましょう。
●加齢
口腔乾燥で最も多い原因がこれです。全身の臓器と同様に年齢を重ねると唾液腺の機能も低下してきます。それと併せて、唾液腺が萎縮(小さくなること)ため、唾液の分泌量が少なくなります。
●糖尿病
糖尿病患者では血糖値が高くなることが多いですが、これが直接的に唾液の質や量に影響を及ぼすことがあります。高血糖は体内の水分バランスを崩し、脱
水症状を引き起こすことがあります。脱水は唾液の分泌減少を引き起こし、結
果的に口腔乾燥につながります。
●ストレス
ストレスは交感神経を活性化させ、副交感神経の活動を抑制します。副交感神
経は唾液の分泌を促す役割を持っているため、その抑制により唾液腺の活動が
減少し、口腔内の乾燥が生じます。緊張で口が渇くのもこの作用によるもので
す。
●口呼吸
口呼吸をすると、空気が口内を通過する際に唾液が蒸発しやすくなります。特
に、寝ている間に無意識のうちに口呼吸をしていると、長時間にわたって唾液
が蒸発し続けるため、朝起きたときに口の中が非常に乾燥していることがあり
ます。鼻炎などの鼻疾患や癖などで口呼吸になっている方も注意が必要です
●お薬の影響
高齢社会になった日本では、基礎疾患を持つ患者様が特に高齢者では多くなってきました。心臓の薬、糖尿病の薬、血圧の薬など多くのお薬を1日に飲んでいる方も多いです。お薬の中には、口腔乾燥を副作用とするお薬もあります。気になる方は、薬剤師やお薬を処方される先生に聞いてみてください。
●シェーグレン症候群
口腔乾燥で隠れている可能性のある難病です。シェーグレン症候群は、自分の免疫細胞によって唾液腺や涙腺などの組織が破壊されていく自己免疫疾患です。早期に命が危うくなるといったことはありませんが、様々な症状によって、患者さんの生活の質が下がってしまいます。
たかが口腔乾燥と言ってもシェーグレン症候群のように難病の症状として現れることもあります。また、糖尿病の症状としてお口が乾く、のどが渇くという症状が生じることもあります。
④口腔乾燥への対応
口腔乾燥に正しく対応するには、まずは正しい診断をしなければなりません。お薬が原因であれば、お薬を変更する必要があります。また、加齢が原因であれば人工唾液やお薬を使って、唾液を出しやすくすることもできます。自身の気になる症状があれば、ぜひお気軽に歯医者さんの相談してみてください。
⑤まとめ
さて、今回は口腔乾燥についてお話しました。口腔乾燥は様々な原因で生じます。もしかしたら、糖尿病などの基礎疾患の症状であったり、シェーグレン症候群のような難病の症状として生じていたりすることもあります。まずは、正しい診断が必要になります。もし、気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから。
ご相談・お問い合わせはこちら
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。